
ISDNのデータ通信終了に向けて「インターネットEDIに移行するか否か」「移行するならどの製品に乗り換えるか」を検討する必要性に迫られている企業は少なくない。製品選定のポイントは。

部品調達の重要なインフラであるEDIシステムを三菱自動車がSaaSで運用、災害などの危機対応を強化する。クリティカルシステム向けインフラを採用して実現している。

富士ゼロックスがABS樹脂を超えるウエルド強度を持ったバイオプラスチックを開発。環境配慮型製品開発の選択肢が増えることになりそうだ。

東日本大震災の直後から復旧作業に取り組んだ中央物産だが、その道のりは決して平たんではなかった。システムトラブルが続く小売店も少なくなく、せっかく届けた商品の引き取りを拒まれるケースもあったという。

豊通エレクトロニクスは電機・電子部品技術情報の流通や再利用、業務プロセスの効率化に向けた情報流通基盤サービスを発表した。

入手した情報をいかに活用するか? そうした観点でITを客観的にとらえなければ、企業の成長には結び付かない。その役割を担うCIOに求められる適性を、大手卸売業Paltacの特別顧問である山岸十郎氏の取り組みを基に考える。
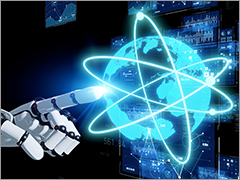
INS回線の提供終了に端を発する「EDIの2024年問題」が大詰めを迎えている。これを機に、受注業務のプロセスを最適化、自動化してDXの第一歩を踏み出す方法を専門家が語った。
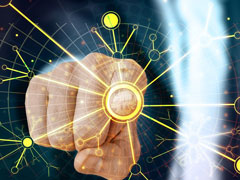
レガシーシステム刷新はDX推進の礎(いしずえ)となるが、特にメーカーや卸売企業はEDIシステムの再構築にも注目しなければならない。EDI再構築のポイントやハマってはいけない落とし穴を解説する。

複合機を導入する際、販売店に勧められるがままにオプション機能を契約したものの、使いこなせていないという企業は少なくない。標準機能で誰でもメンテナンスが簡単にできる複合機はないだろうか?

ISDNのデータ通信が終了することを見据えて、インターネットEDIを採用するなら2022年末までには移行を終わらせるのが理想的だ。タイムリミットまでに準備すべき「接続テスト」と「セキュリティ対策」とは。

2024年1月にISDNのデータ通信が終了するタイミングよりも前に、EDIの通信サービスとシステムの切り替えを終わらせておかないと、どのようなリスクがあるのか。まず確認すべきことは何か。

本連載ではEDIによる業務効率化やマーケティングへの応用について解説してきた。今回は視点を若干変えて、EDIの普及に伴って新たに考えなくてはならない問題について説明したい。

流通業における企業間取引を統合し、受注から出荷報告までのプロセスを可視化する「ACMS/Oracle BPEL Process Manager連携ソリューション」を提供開始する。