Windows管理の在り方が変わりつつある。目指す方向性はMicrosoftが言う「現代的な管理」であり、その鍵を握る複数の要素がある。(続きはページの末尾にあります)

Windows 10のサポート終了を迎え、Linuxへの移行を検討する企業がある。本稿は、Linux導入のステップや注意点、最適なディストリビューションやハードウェアの選び方を解説する。

2026年、Linuxがエンタープライズ向けワークステーションの選択肢として注目を集めている。その背景にある理由は。

ドメインコントローラーのOSを「Windows Server 2025」に入れ替えて「Active Directory」の刷新を図ることは、さまざまなメリットを生む一方で、複数の注意点が存在する。移行戦略の要点と手順をまとめた。

「UNIX」系OSでファイルやフォルダを操作する際によく見かけるのが、アルファベットや数字から成る“謎の文字列”だ。これらの文字列の意味や使い方とは。実例に沿って説明する。

「システム運用管理」「仮想化」に関するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、2021年度第1四半期に新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

「Windows」に関する話題を紹介するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

Microsoftは2026年1月26日、Wordに存在するセキュリティ機能のバイパス脆弱性(CVE-2026-21509)に対応するOffice 2016向けの更新プログラム(KB5002713)を公開した。

Windowsの挙動には“クセ強仕様”が潜んでいる。長いパスが拒まれ、特定名が使えず、謎のフォルダが肥大化する。背景を知ると、意外な理由が見えてくる。

「Windows 10」のサポート終了は、ユーザーに「Windows 11」へのアップグレードを迫っている。Windows 11を新たに導入する際の障壁は何か。Windows 11の台頭で今後ニーズが拡大するのはどのようなPCか。

2026年1月、Windows 11の月例アップデートで複数の不具合が発生した。特に最新CPU搭載機や業務メールに直結する障害は業務運用の課題となる。Windows 11の「こんなはずじゃなかった」にはどのようなものがあるのか。
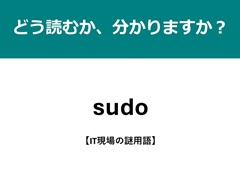
今回取り上げるのは「sudo」です。管理者権限の操作でおなじみですが、正しい読み方は意外と知られていません。見慣れたこのコマンドは、何と読むのでしょうか。

「Windows」系OSが採用してきたファイルシステムには、「NTFS」の他に「FAT」や「HPFS」がある。それぞれどう異なり、なぜNTFSが標準ファイルシステムになったのか。3つを比較し、その特徴と優位性を解説する。

MicrosoftがWSUSの開発終了を発表したが、現場の認知は十分とは言えない。更新管理の遅れは、セキュリティリスクや業務停止を招く恐れがある。多くの企業が次の手段として選んだ、現実的な「移行先」とは何か。

各種セキュリティ製品から収集するログ情報をどう「読む」かが、セキュリティを強化する上での鍵を握る。Excelの「XLOOKUP関数」を使ってログ情報を読みやすくするには。

「Windows 10」のサポート終了まで残りわずかとなった。その後も使い続ける場合、コストとセキュリティリスクの増大に直面する可能性がある。Windows 11への移行に向けて取るべき施策とは。

GoogleはWebブラウザ「Chromium」で、「JPEG XL」形式の画像を扱えないようにする。JPEG XLに未来を感じる開発者が講じるべき回避策とは何か。JPEG XL開発の当事者が提案する。

2016年7月29日に無償アップデートが終了する「Windows 10」。移行をかたくなに拒む動きもあるが、Microsoftが掲げる「2、3年でWindows 10デバイスを10億台へ」という目標は、絵に描いた餅ではなさそうだ。

2015年には、DaaSに大きなニュースがあるはずだと予測した筆者。そのニュースの正体である、「“Microsoft DaaS”の登場」という予想は外れた。その原因は何だったのか。
まず、クラウドベースのデプロイメントとプロビジョニングが挙げられる。これはシステムイメージではなく設定がベースとなる。2番目のID管理と認証は、「Office 365」に使われている「Azure Active Directory」(Azure AD)か、オンプレミスの「Active Directory」とAzure ADの組み合わせを利用する。第3の要素は設定と構成に関するもので、これはグループポリシーではなくモバイル端末管理(MDM)を通じて行う。
グループポリシーは消滅するわけではなく、依然としてきめ細かいコントロール機能を提供する。だがMDMには効率が良く、Windows端末と非Windows端末を管理でき、Active Directoryに依存しないといったメリットがある。
更新プログラムを適用しないPCはセキュリティリスクと化し、Windowsに加わった新機能をユーザーに提供しなければ生産性に影響が出かねない。半面、更新プログラムの配信を急ぎ過ぎると重要なアプリケーションとの互換性に悪影響が出る恐れがある。
Windows 10は、約3年ごとのバージョンアップに代わって、新機能を盛り込んだ更新プログラムが定期的に(現時点では年に2回)配信されるようになった。
例外として、「長期的なサービスチャネル(Long-Term Servicing Channel:LTSC)」は更新プログラムを適用するタイミングを管理者がコントロールでき、またコントロールしなければならない。
Quality Updateはセキュリティ問題や不具合を修正するもので、新機能は追加されない。Feature Updateでは、機能の追加や変更、場合によっては削除が行われる。
Microsoftが導入したサービスチャネルの概念では、それぞれのサービスチャネルがFeature Updateの成熟度を反映する。「半期チャネル(Semi-Annual Channel:SAC)」は一般ユーザー向けの通常チャネルで、半年ごとに機能が更新され、設定によって遅らせることもできる。
IntuneはMicrosoftが提供するクラウドベースの端末管理製品で、現在のIntuneは「Intune Classic」とも呼ばれる最初のバージョンとは異なる。
Intune Classicはモバイル端末ではなくPC向けで、グループポリシーをベースとしていた。Windows 7や1607以前のWindows 10は今もIntune Classicを必要とする。
対照的に、現在のIntuneはPCとモバイル端末を管理できる。Azure ADに依存し、端末の登録は手作業で行う方法(ユーザーが自分のPCに業務用のAzure ADアカウントを追加する)と、PCがAzure ADに参加している場合に自動的に行う方法がある。
「ハイブリッドAzure AD」は、ドメイン参加サーバにインストールされたIntune Connectorコンポーネント経由で、Active DirectoryとAzure ADの両方に参加する。
Intuneを使った更新管理はWindows 10の更新リングをベースとする。更新リングはコンピュータやユーザーのグループに割り当てられた設定で、特定の更新チャネルをベースにして通常は半期チャネルか半期チャネル(ターゲット指定)のいずれかを割り当てる。Windows管理者がWindows Insiderチャネルを設定することもできる。
IntuneはWSUSやSCCMに比べ、Windows更新の設定がはるかにやりやすい。何よりも、サーバのインストールや設定をする必要がない。