マルウェアによる情報漏えいを防ぐには、マルウェア対策ソフトウェアを最新状態に保つことや、マルウェアによって起きる脅威を従業員に周知することが必要になる。(続きはページの末尾にあります)
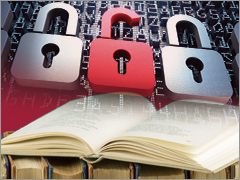
買収劇で混乱するTwitter社に、セキュリティ専門家は厳しい視線を向ける。同社の情報漏えい事件を“予言”した人さえいる。「Twitter」は安全なのか。

質の高いセキュリティ教育を提供する教育機関を評価する認定制度が「CyberFirst Schools」「CyberFirst Colleges」だ。どのような認定制度なのか。運営する英国NCSCに、その詳細と意義を聞いた。

ロシアによる侵攻の影響を受けるウクライナ語話者向けに、EdTechベンダーBabbelが言語学習コースの無償提供を始めた。どのようなものなのか。

「セキュリティ」に関するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、2021年度上半期に新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

auカブコム証券は内部・外部不正対策として複数ログを相関的に分析している。巧妙化するサイバー攻撃の対策として同社が目指すこととは。

膨大なログを相関的かつ効率的に分析できる内部不正検出システムを導入したauカブコム証券。その効果とは。同社担当者が語る。

インターネット証券会社のauカブコム証券は、さまざまなログを分析して内部不正対策に取り組んでいる。だがそこには人手だけでは対処し切れない課題があった。それはどのようなものか。

IBMがリムーバブルストレージの使用を禁止し、従業員に社内ファイル共有システムの使用を促している。こうした禁止措置はセキュリティ強化につながるのか。
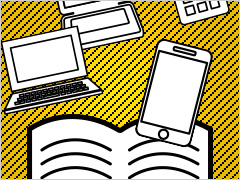
SNS大手Facebookからの個人情報流出は、最大8700万人に影響する大きな問題となった。だがFacebook以外のSNSなら安全とは言い切れない。便利なSNSに潜む脅威を追う。

今、ハニーポットなどで収集した情報をセキュリティ対策に積極的に活用するディセプション(欺瞞)技術が注目されている。その概要と展開に際しての注意点を紹介する。

IT部門責任者を対象とした調査によると、彼らはサイバー攻撃を恐れ、適切な対策が取れていないことを懸念している。にもかかわらず、IT部門責任者たちは現状認識について驚くべき回答を寄せた。

企業や個人にとって身元確認情報、つまりIDの管理は難題だ。しかし、仮想通貨で話題のブロックチェーンがその簡素化に役立つという。
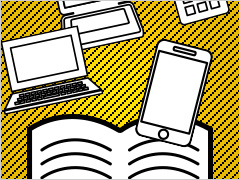
Appleが「iPhone」シリーズの最上位機種として発表した「iPhone X」。その目玉機能である顔認証「Face ID」の安全性に懸念の声が挙がっている。単なる臆測なのか。それとも……。

日本政府は、2020年の東京オリンピックに向けてさまざまなサイバーセキュリティ対策を進めている。政府の対策は十分なのか。そして、オリンピック開催時にやって来る「膨大な脅威」とは何か。

サイバーセキュリティの認定資格が無数にある。駆け出しの新人が最初に取得すべき資格はどれだろうか。

セキュリティ業界で実施されたアンケートにより、使用頻度が高い攻撃手法トップ10が明らかになった。特に上位の手法に注目して、対策方法を紹介する。

ロンドンのHIV専門クリニックが、HIV患者の情報を漏えいしてしまった。原因は単純なミスだった。このようなことがなぜ繰り返されるのか?

サーバやセキュリティのログを分析してサイバー犯罪や社内の不正に対処し、ユーザーエクスペリエンスを最適化する紹介する。

Apple Payを使うとカード番号が盗まれる危険性がある……。米セキュリティサービス企業が発表したハッキング手法とは?
企業が情報漏えいに対処するには、相応の時間や人員を割かなければならない。その結果、他の業務に影響が及ぶ。情報漏えいが発生したら、その事実を顧客に知らせなければならない。この知らせを受けた顧客が、自社の提供サービスを利用することをやめる恐れがある。情報漏えい後に顧客との信頼関係を再び築くには、時間と手間が必要になる。
従業員による情報漏えいを防ぐために、企業は重要なデータや機密データへのアクセスを、必要最低限の担当者のみに制限する必要がある。データへのアクセス制御は、攻撃者によるデータの損失に加え、従業員が意図せずデータを消去するといった人為的ミスを防ぐのにも役立つ。
情報漏えい対策のためのソフトウェアやサービスの購入により、ITコストが増大する可能性がある。こうしたコストが高額になるとしても、データに対する保護を徹底することで、サイバー攻撃の被害を受けた際にかかるコストを抑えられる。
「DLP」(データ損失防止)は、インシデントが発生したときの、情報漏えいやデータ損失の被害の軽減や防止を目的とする技術だ。DLP製品は従業員が転送または共有できるデータを制限することで、情報漏えいを抑止する。
従業員が機微なデータや機密データの扱い方を誤ったり、悪意を持って漏えいしたりしないように、データを保護する上でDLP製品は役立つ。DLP製品の導入は、企業のデータ保護戦略の重要なポイントになりつつある。
主要なDLP製品やサービスには、Microsoftの「Microsoft 365データ損失防止」、Broadcomの「Symantec Data Loss Prevention」、McAfeeの「McAfee Total Protection for Data Loss Prevention」などがある。