「AIOps」は、システム運用(Ops)に人工知能(AI)技術を用いることを表す。機械学習(ML)などのAI技術で、システムに生じる問題の特定と解決を自動化する。企業のシステムは、ログをはじめとするさまざまなデータを生成している。AIOpsツールはこれらのデータを使ってシステムを監視し、システム同士の依存関係を可視化する。(続きはページの末尾にあります)

セキュリティツールの一種であるSIEMは有用だが、真価を発揮させるのは容易ではない。だがAIを運用に応用することでSIEMを活用できる可能性が開ける。

「DataStax Vector」は、OSSのデータベース「Apache Cassandra」の運用をサポートするAIOpsサービスだ。このサービスによって何が実現するのか。

「AIOps」ツールがあれば、ITインフラの管理を効率化できる可能性がある。だが人手を介さない自動化機能でどこまで対処できるかは、依然として議論の余地がある。
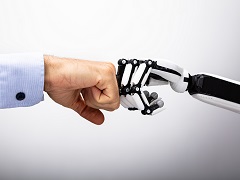
IT運用のさまざまな領域にAI技術が入り込んでいる。AIOpsを実践中のアクセンチュアは、自動化の適用範囲をさらに広げることにまい進する。同社が次に狙う成果とは。
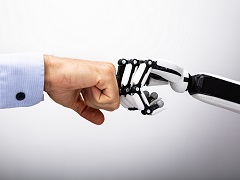
ITコンサルティング会社のAccentureは、機械学習でIT運用を自動化する「AIOps」によって社内の業務負担を軽減している。同社が実践するAIOpsの取り組みと、その成果とは。

IT運用の人材やスキルの不足が課題として挙がる中、システム運用にAI技術を使う「AIOps」はどう役立つのだろうか。地方銀行のKeyBankはAIOpsをどう活用しているのか。

世間をにぎわす「生成AI」ブームはいつ始まって、どう拡大してきたのか。各主要ベンダーは生成AIをどのようなツールに組み込んでいるのか。主要な動きを紹介する。

コストを抑えつつ自由にカスタマイズできるのが、オープンソースソフトウェアの利点だ。「AIOps」ツールもその例外ではない。OSSのAIOpsツールを俎上(そじょう)に乗せる。

生成AIは、IT運用のスキルギャップ解消に具体的にどのように役立つのか。スキルギャップが解消された際に重要となるのはどの要素なのか。

「AIOps」ツールはシステムの運用や開発における業務効率化に役立つ。どのようなメリットがあり、どのように活用できるのか。似た言葉である「MLOps」と共に紹介する。

普及してはいるものの、AI技術の中ではそれほど目立った存在ではない「自然言語処理」技術。実は「ハイパーオートメーション」では重要な役割を果たし得るという。どういうことなのか。

クラウドや分散システムの普及により、システム運用はますます複雑化している。「AIOps」でAI技術を活用することで、運用の効率と精度を飛躍的に高めることが可能になる。AIOps導入のステップやこつを解説する。

AIOpsツールでは、予測分析、正常性評価、予防措置の提案が可能になる。発生した問題に反応して解決するために面倒な作業全てをこなす管理業務はなくなる。

管理・監視ツールが自分の代わりに考えてくれて、セルフサービスITインフラが、ボタンを押すだけでデプロイされる環境の中で、IT運用担当者は何をすべきだろうか。

生成AIをはじめとするAI技術が進化する中で、企業が人間よりもAI技術を信じるようになるのではないかという懸念が出ている。専門家はこうした見方を否定する。どのような未来を見ているのか。

米国の新興企業、BigPandaは6回目の資金調達を終え、幅広い業種への提案活動に本腰を入れる。AIを使ったシステム運用の自動化ツールを手掛ける同社はなぜ今、投資家からの期待を集めるのか。

ERPベンダーは、拡張現実(AR)や人工知能(AI)といった先進的な技術の導入を後押しする役割を果たすかもしれない。だが、IT予算の締め付けが続いており、そうした技術の売り込みは難航する可能性がある。
AIOpsツールは、次の3つのメリットを企業にもたらす。
IT担当者の日常業務には、エンドユーザーの需要に応じたシステムのリソース確保や、重要性の低いシステムのアラートへの対処などがある。IT担当者はAIOpsツールを使うと、例えばシステムへのアクセス量が増大した際のリソース拡張を自動化できる。
マルウェア攻撃やシステムの怪しい挙動に、IT担当者が気付かないことがある。重要なシステムの挙動が通常の動作から外れる場合、AIOpsツールはサイバー攻撃やマルウェア感染の可能性があると捉え、優先的に問題の解決に当たる。
AIOpsツールは各システムから取得したデータを監視、分析し、IT部門の各チームに適切な情報を表示する。それぞれのチームは情報の共有や解析のために会議を実施したり、関連データを手作業で送信したりする手間を減らすことができる。
AIOpsツールには、以下のような製品が挙げられる。
既存のインフラ監視ツールにAIOpsの機能が含まれている場合もある。New Relicの「Applied Intelligence」(NRAI)は同社のインフラ監視ツール「Digital Intelligence Platform」で利用できるAIOps機能で、発生したアラートの対処を自動化する。