
「Slack」から「Microsoft Teams」や「Google Chat」といった他ツールへの乗り換えを検討する場合、その判断が妥当かどうかを見極めるにはどのような点を検討すればいいのか。移行に失敗しないためのこつとは。

Slackから別のコラボレーショツールに乗り換える企業は、コスト削減や経営戦略だけを理由にしているわけではない。企業が乗り換えに踏み切っている背景を探る。

かつて「Skype」はコミュニケーションツールの主役だったが、現在はかつての勢いはない。「Zoom」など比較的新しいWeb会議ツールの普及が影響していることは確かだ。だが衰退の原因は本当にそれだけなのだろうか。

「データ分析」「情報系システム」に関するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、2021年度上半期に新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

ビジネス界のリーダーたちは言う。社員間の信頼を築きコラボレーションを支援するため、企業の経営陣はコラボレーションツールの「Slack」を導入すべきだと。

オンライン英会話サービスを提供するレアジョブ。開発部門を中心に、社内のコミュニケーションツールを「Skype」から「ChatWork」へ移行した。移行のいきさつと社内がどのように変わったかを紹介する。

Googleが生成AI「Gemini」を「Googleドキュメント」「Gmail」などに導入することを発表した。エンドユーザーは、どのような機能を使用できるのか。コストに見合う効果は期待できるのか。
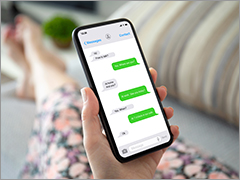
顧客や取引相手とのやりとりにおける「電話がつながらない」「メールを読んでもらえない」といった事態は、連絡業務の負荷を大きくする。SMSならこうした課題を解決できる可能性がある。「本人確認」だけではない、SMSの新しい使い道とは。

今や企業の情報共有手段はメール、電話からチャットツールに移りつつある。しかし、チャットツールといっても千差万別だ。最近のツールはどれも豊富な機能を備えているものばかりだ。選定のポイントはどこにあるのか。

メッセージングアプリケーション「Telegram」を手掛けるTelegram MessengerのCEOが逮捕された。犯罪行為に悪用された責任を、ツールの提供事業者どこまで追う必要があるのか。Telegramは今後どうなるのか。

コンプライアンスやリスク管理、ガバナンスの保持を前提としたコラボレーションツールの使用ルールを社内で徹底させるには、IT部門と“あの部署”の連携が重要な鍵を握る。

コンプライアンスの問題を回避するために、コラボレーションツールの特定機能を使えないように制御するのは一つの方法だが、シャドーITを生むリスクがある。米国金融機関の事例から、注意すべきポイントを探る。

Z世代で大学生の筆者は、米TechTargetの編集チームでインターンシップに参加し、その経験から社会人や編集者としての基本の「基」を学んだ。その内容を紹介する。

ある調査結果によると、労働者としてのZ世代に対して企業からの風当たりは強い。米TechTargetでインターンを務めたZ世代の大学生が、インターンの経験から得た学びや成長のきっかけになった出来事を紹介する。

Z世代が労働力として活躍する時代になった。一方で、ビジネスの場では「Z世代は仕事ができない」と見なされる傾向がある。それはなぜか。Z世代の特徴と併せて考える。

生産性や離職の決断に、“ある要因”が大きく影響する可能性があるという実態が見えてきた。企業がテレワークの継続や出社回帰などの決断を下す中で、生産性や離職に大きく影響している要因とは何か。

従業員による「メッセージングアプリ」の業務利用が問題となっている。米国では罰金支払いに発展した。どのようなリスクが潜んでいるのか。

米国の大手銀行が、銀行員のメッセージングアプリケーション利用を巡る問題で、規制当局から罰金支払いを命じられた。何が問題となったのか。