
私物端末の業務利用「BYOD」を解禁しても、事前の検討が不足していると期待通りの効果が得られなかったり、思わぬリスクを負ったりする可能性がある。BYOD採用前に確認すべき点を整理しよう。

小中学校が授業でのIT活用を進める上で、最も基本となる2製品がある。電子黒板をはじめとする「大型提示装置」と、「実物投影機」がそれだ。それぞれの特徴と選定ポイントを解説する。

教育機関でIT製品を導入する際、製品や使い方を全校で統一すべきなのか。それとも教員の裁量に任せるべきなのか。教員志望の学生と教員との座談会の内容を基に考える。

学習者一人一人がタブレットを持ち、板書を電子的に共有可能にした環境であれば、学習者は板書の書き写しに忙殺されなくて済む。それは良いことばかりなのだろうか。教員志望の学生と教員が議論する。

教員を目指す学生は、教育機関で進むIT活用にどう向き合い、どうITを活用しようとしているのか。教員との座談会から明らかにする。

教育機関のIT活用に関する話題の中で、TechTargetジャパン会員が最も関心を寄せたものとは。2017年のアクセスランキングから読み解きます。

タブレットを効果的に生かすには、利用するアプリケーションの選定が大きな鍵となる。タブレット活用に先駆的に挑む教育者チーム「iTeachers」の注目アプリケーションを知ることは、選定の参考になるはずだ。

教育活動にいち早くITを生かしてきた教育者チーム「iTeachers」。そのメンバーが挑む、IT活用の具体的な事例をピックアップして紹介する。

千葉県立千葉工業高等学校が進めるのは「9.7インチiPad Pro」の導入だけではない。生徒による無線LAN環境の構築など、工業高校ならではともいえる取り組みも進む。実態を見ていこう。

プログラミング教育やSTEM教育を支援するIT製品/サービスには、どのようなものがあるのか。同分野の専門ブースを新設した2016年の教育ITソリューションEXPOの展示内容から、その最新動向を探る。

学校生活にITを使いこなしてきた大学生が、IT活用の拡大に悩む教育機関にアドバイス。その内容とは? 千葉大学1年の山本恭輔さんに聞きます。

教育機関にとって、タブレットをはじめとするデバイスの管理とコスト負担をどうするかは大きな課題だ。採用が進む「BYOD」は、この課題の適切な解決策となり得るのだろうか。
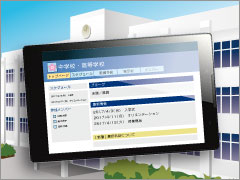
生徒1人1台のタブレット環境を生かすべく、無料のグループウェアを使って学習ポータルサイトを構築したのが立命館宇治中学校・高等学校だ。その選定理由や活用方法とは。

IT活用を進める上で、教育関係者が直面する課題は少なくない。ITを活用した学習手段の充実を前に、保護者や学習者が抱く疑問もある。先駆的なIT活用を進める教育者集団が、こうした課題や疑問を議論する。

成功例に注目が集まりがちな教育機関のIT活用。だが先駆的なIT活用校が経験しているのは成功体験だけではない。玉川大学とデジタルハリウッド大学の教員と学生が、IT活用の課題を語り合う。

休み時間にもかかわらず、生徒が英単語学習をしたくなるというiPadアプリとは? 佐賀市立大和中学校の中村純一教諭が明かします。

12.9インチの大画面タブレット「iPad Pro」を使った、新しいノートの取り方とは? 佐賀市立大和中学校の中村純一教諭が説明します。

英語教室「キッズイングリッシュ」の新米講師が、生徒から不評だった英単語学習をどう変えたのか? 同教室の代表を務める金谷尚美氏が明かします。

タブレットの導入当初は思うように活用が進まなかったという桜丘中学・高等学校。その理由と、解決のための工夫とは? 同校職員の西岡朱里氏が明かします。

救命救急士の育成にITを生かす、国際医療福祉専門学校の救急救命学科。IT導入に至ったいきさつとは? 同学科でIT活用を推進する学科主任の小澤貴裕氏が明かします。