クラウドストレージは、ストレージシステムのクラウドサービスだ。ユーザー企業はクラウドベンダーが運用するストレージシステムにデータを転送し、保管する。インターネットや専用線などの閉域網を通じて利用できる。ストレージ使用量に応じて、月ごとに利用料金が発生するのが一般的だ。(続きはページの末尾にあります)

世界的なデータ量の増大で、ストレージの需要が高まっている。しかしHDDやSSD、テープといった従来のストレージは、データの記録密度や耐久性に限界がある。Microsoftが開発中の“透明なストレージ”は、こうした課題の突破口となるのか。

SaaS利用時に契約内容を詳細に確認していないと、思わぬ落とし穴にはまる可能性がある。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔せずに済むように、押さえておきたいチェックポイントを紹介する。
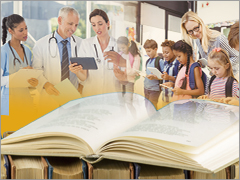
医療機関が災害に備えて医療データを保護する上で有効な手段となるのが、災害復旧(DR)にクラウドを活用することだ。クラウドベースのDRを導入する際に考えるべき5つのポイントを紹介する。

中小企業が大企業と同レベルの事業継続性を実現しようとすれば、当然ながらヒト・モノ・カネの問題にぶつかる。ただし近年はサービスの進化によって、大企業に匹敵する対策も不可能ではなくなっている。

料理番組を制作するAmerica's Test Kitchenは、オンプレミスのストレージとクラウドストレージを使い分けてデータを保管している。どのような仕組みで運用しているのか。使い分ける理由は。

パンデミックが発生して以降、遠隔で共同作業をすることは珍しくなくなった。大容量のファイルを扱う必要のある映画業界は、どのような手法を取り入れたのか。

テレワークに移行したことを機に、バックアップシステムを見直した米国の2年制大学MVCC。同校のITインフラの責任者は、ある理由からテープにもクラウドストレージにも不満を持った。最終的に下した決断とは。

環境意識の高まりやエネルギー価格の高騰を背景に、環境に配慮した形でストレージを運用する動きが加速している。どう運用すればよいのか。具体的な方法を紹介する。

広告事業のFrance Televisions Publiciteは、バックアップやアーカイブのシステムをクラウドサービスからオンプレミスのインフラに戻した。同社はクラウドサービスに「不便さ」を感じたという。それは何なのか。

America's Test Kitchenは「Amazon S3」とオンプレミスのストレージアプライアンスを併用するデータ保管の仕組みを構築した。導入した製品やその狙いは。

北米やアジアに複数の拠点を擁する建築会社が、ストレージをオンプレミスからクラウドNASに移行。各地からのファイルアクセスとコスト削減に成功した。

「セキュリティ」に関するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、2019年度にユーザー企業の新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

映像配信サービス「ひかりTV」を運営するNTTぷららは「Azure Blob Storage」のデータをオンプレミスに移行した。大量のデータをクラウドではなくオンプレミスに置くことを選んだ理由は何だったのか。

使っていないもの、余っているものを共有し、対価を得る。これをストレージに適用するとどうなるのか。Storjの挑戦は成功するのか。成功の条件とは何か。

ティム・バーナーズ=リー氏がInruptという企業を立ち上げた。その狙いは、オンラインデータの管理権限をそのユーザー自身に与えること。そのためのプラットフォーム「Solid」とは? 同氏が目指すWebとは?

PCやネットワーク、ファイルサーバにセキュリティポリシーを適切に適用している組織は多いだろう。だが、機密文書や個人情報は意外な所に保存されている可能性がある。

調査の結果、大多数の企業がソフトウェア保守契約を検討せずに更新していることが明らかになった。だがその保守契約から何らかの価値を得ているだろうか。

ハイブリッドクラウドに対応したオブジェクトストレージを使うと何が実現するのか。両者の特長を生かすことによって、データを柔軟に運用できるようになる。

社内アプリケーションをクラウドで利用する手段はさまざまだ。最近注目されているマルチテナント型は、シングルテナント型に比べ、維持管理の面で大きな効果を発揮するという。

中小企業でも手が出る価格のクラウドサービスが登場。会計から生産管理、在宅勤務まで、多様なサービスを1つのサイトで購入できる。
クラウドベンダーは、仮想化して集約(プール化)したストレージをクラウドストレージとして提供する。クラウドストレージは、ユーザー企業がストレージを利用するための管理コンソールを備える。ストレージ容量は瞬時に拡張・縮小できる。
ユーザー企業がクラウドストレージに転送したデータの保存先は、クラウドベンダーのストレージプールだ。このストレージプールは、クラウドベンダーのデータセンター内にある複数のストレージシステムで構成される。これらのストレージシステムは、一般的にはクラウドベンダーが運用する複数のデータセンターに分散している。
クラウドストレージでは、ストレージシステムを運用管理するのはクラウドサービスベンダーの役割だ。ユーザー企業は、クラウドストレージをオンデマンドで利用でき、自社でストレージシステムの購入や管理、運用をする必要がなくなる。
ユーザー企業は公共料金の支払いと同じように、ストレージの使用量に応じて料金を支払う。データへのアクセスの頻度やクラウドベンダーのデータセンター外に転送するデータ量に応じて、追加の利用料金がかかる場合がある。
主要なクラウドストレージは以下の通りだ。