
「RF1」「神戸コロッケ」などの総菜を手掛けるロック・フィールドは、災害復旧(DR)システムを刷新。ストレージの容量不足の問題を抱えていた同社が「Veeam Backup & Replication」で実現した手法と成果は。

Commvault SystemsとZertoのDR(災害復旧)製品は、共に充実した機能を備える。どのような違いがあるのか。API連携やライセンスの観点で両製品を比較する。

DR(災害復旧)製品を使うことでミッションクリティカルなシステムの稼働を維持する方法がある。Commvault Systemsの「Commvault Disaster Recovery」と、Zertoの「Zerto Enterprise Cloud Edition」の仕組みや機能を比較する。

サーバ障害やサイバー攻撃によるシステム停止は、もはや想定外では済まされない。Veeam Softwareの年次カンファレンスでは、MLB球団や教育機関の事例を通じて、DR計画や仮想化基盤の見直しについて語られた。

ランサムウェア攻撃を受けたLEO A DALYがデータを迅速に復旧させるために、クラウドファイルストレージの機能が役立った。同社はなぜクラウドファイルストレージを使うことにしたのか。

ランサムウェア攻撃の標的になった建築設計事務所のLEO A DALYは、暗号化されたデータを数時間で復旧させることができた。なぜ早期復旧が可能だったのか、その理由を探る。

2024年に「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたことは記憶に新しい。サイバー攻撃の脅威に加えて、このような自然災害のリスクにもさらされている日本企業が、いま考えるべき「迅速に復旧可能な仕組み」について、有識者に聞いた。

ITシステムが停止してしまうリスクには、「ハードウェアの故障」「ソフトウェア障害」「サイバー攻撃」「自然災害」「人為的ミス」の5つがある。これらがビジネスに与える影響を最小化できる低コストで高度なDR環境とはどのようなものか。
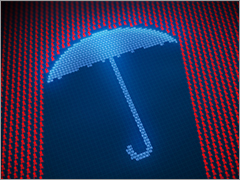
自然災害に備えてBCPを見直すならば、通信障害対策を忘れてはいけない。電話やインターネットが使えなくなる事態に備えて、何を用意すればよいのか。平時にも役立つ対策を紹介する。

RAIDはバックアップやストレージ運用の基本となる技術だ。RAIDの種類の中でも広く使われている「RAID 5」と「RAID 10」の違いを解説する。

「BCP」「DR」「インシデントレスポンス」は、非常事態に業務を継続するための対策として欠かせないものだ。それぞれを実施する際の要点は何か。ベストプラクティスを紹介する。

ビジネスを継続するためには、システムをいかに停止させないかが重要になる。そのために欠かせないのが「BCP」「DR」「インシデントレスポンス」だ。3つの違いと、具体的な取り組みとは。

システム障害はもはや「事故」ではない。7割超の企業が1時間以上のシステムダウンを経験し、全体の4社に1社が1000万円超の損失を被っている。なぜ被害が拡大するのか。現場を苦しめる「対策の死角」を暴く。

2026年に向けて、IT管理者が押さえるべきバックアップの主要トレンドにはどのようなものがあるのか。後編では5つを紹介する。

ユーザー企業がどれだけ気を付けていても、クラウドサービスの障害は避けられない。クラウドサービスを利用中の企業が障害の影響を抑えるための事前準備として、何に取り組むべきなのか。

DR(災害復旧)分野にはさまざまな専門用語が存在する。似た用語の混同はDR計画の致命的欠陥になり得る。担当者が正確に理解しておくべき、12個のDR用語を取り上げる。

DR(災害復旧)関連の用語を誤解していると、危機的状況下での対処が遅れる可能性がある。企業の復元力を高め、事業を継続させるために知っておくべき8つのDR用語とは。

災害やサイバー攻撃でシステムが停止した際、DR(災害復旧)用語の理解不足が復旧の大きな障壁になり得る。知っておかないと現場で混乱しかねない、7つのDR用語を解説する。