「ビジネスインテリジェンス」(BI)は、経営者や従業員が十分な情報に基づいた意思決定をするためのデータ分析の手法だ。BIを実現するために、企業は自社のITシステムや外部のリソースからデータを収集して、分析用に準備する必要がある。(続きはページの末尾にあります)

「Tableau」「Power BI」「Qlik Sense」はほぼ同等のセルフサービスBI機能を提供するが、いずれの製品にも長所と短所がある。コンサルタントのリック・シャーマン氏に話を聞いた。

「セルフサービスBI」の主要2ツール「Tableau」と「Qlik Sense」は、互いに似たものになりつつある。高度な視覚化機能と大規模データ分析に対するニーズの高まりが、その背景にある。

GartnerがBI/BA製品に関する2016年版の評価レポート「Magic Quadrant」(マジッククアドラント)を発表した。ベンダーのランキングには幾つかの大きな変化があった。

企業はインメモリデータマート向けのSAP HANAと、他のデータウェアハウスを統合したSAP Business Warehouseを利用している。

地理情報の活用はとりわけ新しいものではない。だが、「ロケーションインテリジェンス」(LI)と呼ばれる一般のビジネスユーザー向けの手軽なツールによって、新たな形で地理情報の活用が拡大している。

SAPジャパンは、「SAP HANA」のサービスパック8(SP8)の提供を開始した。「Red Hat Enterprise Linux」(RHEL)対応、予測解析機能の強化、クラウド連係などを実現している。

ビジネスの現場では、過去に起こったことを見るよりも、今後起こり得ることを予見することが重要になった。「SAP Predictive Analysis」を提供開始したSAPジャパンの意志もそこにある。

データを多角的・多面的に分析する予測分析製品群「SAS Analytics」。連携が容易な幅広い製品ラインアップで、現状分析から予測まで一気通貫でカバーする。

ビッグデータに潜む関連性やパターンを視覚的に把握したい――。こうしたニーズに応える製品「SAS Visual Analytics」の新版が登場した。予測分析機能の追加が目玉だ。

OracleがCedarCrestoneに知的財産権を侵害されたとして提訴した。サードパーティーによるメンテナンスを提供させないため、脅しをかける狙いがあると専門家はみる。
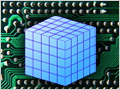
SAP HANAなどで注目を集めるインメモリアナリティクス。アナリストは、「購入前にインメモリアナリティクスツールの各カテゴリーがどのような目的に最適かを把握すべき」と指摘する。

スマートフォンやタブレットといったモバイルプラットフォームでBIを活用できる環境が整ってきた。医療機関従事者のためにモバイルBIの機能、使い方を紹介する。
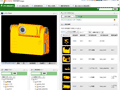
図面、クレーム情報などの非構造化データを、サーチアプリケーション経由で統合管理できる製品が登場。XVL属性情報も丸ごと取り込める。

SAPはインメモリデータベース「SAP HANA」を「SAP Business One」ユーザー企業の中堅・中小企業(SMB)向けに提供予定だ。その狙いは何か、そしてSMBにニーズはあるのか?
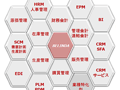
日立ソリューションズが、製造業・流通業に特化したITシステムを包括的に提供する体制を発表。財務システムからPLM、SCMなどを含む広範な業務システムを「ワンストップ」で提供できるのが強み。

将来有望な有機EL照明に関する国内有力特許の調査結果がまとまった。なかでもコニカミノルタホールディングスと富士フイルムの特許総合力が強いという。

2012年上半期に提供を開始する「SQL Server 2012」。マイクロソフトのビッグデータ対応戦略とともに、SQL Server 2012の新機能を紹介する。

複数のERP製品で構成する「Infor10」が発表された。コンシューマアプリケーションを参考にインタフェースを開発するなど、使いやすさやアプリケーション間の接続にしやすさが特徴だ。

SAPが3次元データ管理および基幹システム連携機能を提供する企業を買収。サポート・メンテナンス部門、販売部門との連携強化や質の高いモバイルコミュニケーションが期待できる。

BIのスマートデバイス対応は単なるトレンドなのか? 日本オラクル、SAPジャパンが言う「真のリアルタイム」をひも解くと、それがもたらすユーザーメリットが見えてくる。
BIツールは、収集したデータを分析し、ダッシュボードで分析結果を可視化したり、レポートを作成したりする。ユーザー企業はBIツールの分析結果を、業務の意思決定や戦略立案に役立てることが可能だ。
自社の収益の増加や業務効率の向上、ライバル企業よりも強い競争力の獲得のために、より良い意思決定を促すことが、BIの目標だ。この目標を達成するために、BIツールはデータ分析やデータ管理、レポート作成機能を備えている。
BIツールで扱うデータは通常、組織全体のデータを蓄積する「データウェアハウス」(DWH)や、事業部門ごとのデータを蓄積する「データマート」といったデータストアに格納する。「Apache Hadoop」などの分散データ処理技術をベースにした「データレイク」に格納することもある。
DWHやデータレイクは、分析用データの保管に適している。特にデータレイクは構造化データだけではなく、業務システムから取得したログファイルやセンサーデータ、テキストデータなどの非構造化または半構造化データの保管に使用可能だ。
BIは、さまざまなデータソースからデータを取得する。データソースが生成した生データは、データソースごとのデータの差異を解消して一元的に扱いやすくする「マスターデータ統合」や、データ項目の表記揺れや欠損などを補う「データクレンジング」といった処理をしてから、BIツールで分析に使用できるようになる。
登場当初、BIツールは主にBIやITの専門家が使用することが一般的だった。現在は、経営幹部やビジネスアナリスト、事業部門の従業員が自らBIツールを利用することがある。これは「セルフサービスBI」ツールが進化しているためだ。セルフサービスBIツールは、エンドユーザーが自分でBIデータを分析して可視化したり、ダッシュボードを設計したりできる仕組みになっている。