Windows管理の在り方が変わりつつある。目指す方向性はMicrosoftが言う「現代的な管理」であり、その鍵を握る複数の要素がある。(続きはページの末尾にあります)

「UNIX」系OSでファイルやフォルダを操作する際によく見かけるのが、アルファベットや数字から成る“謎の文字列”だ。これらの文字列の意味や使い方とは。実例に沿って説明する。

「システム運用管理」「仮想化」に関するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、2021年度第1四半期に新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

「Windows」に関する話題を紹介するTechTargetジャパンの「プレミアムコンテンツ」のうち、新規会員の関心を集めたものは何か。ランキングで紹介します。

「Windows 10」を快適かつ安全に利用し続けるためには、端末をどう選び、どう運用すればよいのだろうか。そのポイントを紹介する。

「Windows」が動かなくなった場合のトラブルシューティング手段として、不要なレジストリを整理する「レジストリクリーナー」がある。そのメリットと注意点を整理しよう。

「Windows」のレジストリクリーニングは、遅くなったPCの改善効果はそれほど期待できないが、動かなくなったOSやアプリケーションのトラブルシューティング手段にはなる。どのような効果があるのか。

「Windows 10」が突然動作を停止しても、慌てる必要はない。簡単な操作で問題を解決できることがあるからだ。Windows 10関連のトラブルが発生したときに原因を特定する方法と、簡単な解決方法を紹介する。
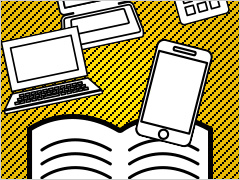
情報システム部門にとって決断の時が迫っている。既に状況は「移行するかしないか」ではなく「どのように移行するか」という段階だ。今、検討すべきポイントとは何だろうか。

Microsoftはマインドシェアを高める必要がある。非Windowsユーザーや非PCユーザーとの関わりをもっと増やさねばならない。モバイルの波で失敗した同社が、デジタルアシスタントの波に乗ることはできるだろうか。

ノルウェーのトロンハイム市は、オンプレミスのMicrosoftアプリからクラウドへの移行を決断。G Suiteを選定し、移行を開始した。彼らは移行を円滑化するため、ある施策を実施した。

Gartnerが発表した調査結果によると、Windows 10への急速な移行によりPC市場がプラスに転じるという。同じく調査結果から、PC市場にはびこる「誤った認識」も否定された。

システムを停止させることなくパッチを適用するホットパッチ機能は、基幹システムにおいて長らく待ち望まれていた。これをまず実現したのはSUSEだった。

Windows XPから7への移行を機会に、仮想デスクトップを利用したゼロクライアント環境を構築。これにより多くの課題が解決し、働き方が大きく変わったという。

USBトークンを利用することでセキュアにユーザー認証を行うFIDO標準。これが普及すればパスワードが不要な世界が実現する。パネルディスカッションの発言から、FIDO標準の現状を探る。

従来型サーバからコンバージドインフラへの移行が増加している。それを裏付ける市場調査の結果から、企業の本音が見えてくる。一方で、コンバージドインフラへの移行をためらう企業の理由とは?

Microsoftは、IE8、IE9、IE10のサポートを終了する。ブラウザベースのアプリケーションを多く抱える企業は、社内アプリケーションの見直しが急務だ。

Windows 10がリリースされてもPC市場の低迷を止めることはできなかった。そのPC業界が期待を寄せるのが、第6世代Intel Coreプロセッサだ。

Googleが、保有する特許をテクノロジー企業50社に無償譲渡すると発表。この大盤振る舞いにはもちろん裏がある。Googleの真の目的とは? 特許を譲渡された企業のメリットとは?

クラウドソフトウェアを開発しているLeadDeskは、開発サイクル短縮のためテスト自動化ツールを導入。リリースサイクルは大幅に短縮したが、導入効果はそれだけではなかった。

低迷していたWilliamsだが、2014年からコンストラクターズ3位圏に復活。さらに上を目指すため、同チームは高速ネットワークを導入した。その導入効果は、意外なところにまで及んでいるという。
まず、クラウドベースのデプロイメントとプロビジョニングが挙げられる。これはシステムイメージではなく設定がベースとなる。2番目のID管理と認証は、「Office 365」に使われている「Azure Active Directory」(Azure AD)か、オンプレミスの「Active Directory」とAzure ADの組み合わせを利用する。第3の要素は設定と構成に関するもので、これはグループポリシーではなくモバイル端末管理(MDM)を通じて行う。
グループポリシーは消滅するわけではなく、依然としてきめ細かいコントロール機能を提供する。だがMDMには効率が良く、Windows端末と非Windows端末を管理でき、Active Directoryに依存しないといったメリットがある。
更新プログラムを適用しないPCはセキュリティリスクと化し、Windowsに加わった新機能をユーザーに提供しなければ生産性に影響が出かねない。半面、更新プログラムの配信を急ぎ過ぎると重要なアプリケーションとの互換性に悪影響が出る恐れがある。
Windows 10は、約3年ごとのバージョンアップに代わって、新機能を盛り込んだ更新プログラムが定期的に(現時点では年に2回)配信されるようになった。
例外として、「長期的なサービスチャネル(Long-Term Servicing Channel:LTSC)」は更新プログラムを適用するタイミングを管理者がコントロールでき、またコントロールしなければならない。
Quality Updateはセキュリティ問題や不具合を修正するもので、新機能は追加されない。Feature Updateでは、機能の追加や変更、場合によっては削除が行われる。
Microsoftが導入したサービスチャネルの概念では、それぞれのサービスチャネルがFeature Updateの成熟度を反映する。「半期チャネル(Semi-Annual Channel:SAC)」は一般ユーザー向けの通常チャネルで、半年ごとに機能が更新され、設定によって遅らせることもできる。
IntuneはMicrosoftが提供するクラウドベースの端末管理製品で、現在のIntuneは「Intune Classic」とも呼ばれる最初のバージョンとは異なる。
Intune Classicはモバイル端末ではなくPC向けで、グループポリシーをベースとしていた。Windows 7や1607以前のWindows 10は今もIntune Classicを必要とする。
対照的に、現在のIntuneはPCとモバイル端末を管理できる。Azure ADに依存し、端末の登録は手作業で行う方法(ユーザーが自分のPCに業務用のAzure ADアカウントを追加する)と、PCがAzure ADに参加している場合に自動的に行う方法がある。
「ハイブリッドAzure AD」は、ドメイン参加サーバにインストールされたIntune Connectorコンポーネント経由で、Active DirectoryとAzure ADの両方に参加する。
Intuneを使った更新管理はWindows 10の更新リングをベースとする。更新リングはコンピュータやユーザーのグループに割り当てられた設定で、特定の更新チャネルをベースにして通常は半期チャネルか半期チャネル(ターゲット指定)のいずれかを割り当てる。Windows管理者がWindows Insiderチャネルを設定することもできる。
IntuneはWSUSやSCCMに比べ、Windows更新の設定がはるかにやりやすい。何よりも、サーバのインストールや設定をする必要がない。