パブリッククラウドは、ユーザー企業が遠隔地からインターネットを通して、必要な分だけリソースを利用可能にするクラウドサービスを指す。利用可能なリソースには、仮想マシンやストレージなどが挙げられる。(続きはページの末尾にあります)

JALカードがIBMの「IBM Power Systems Virtual Server」を採用した事例や、IDC Japanのクラウド利用状況調査の結果など、クラウドに関する主要なニュースを紹介する。
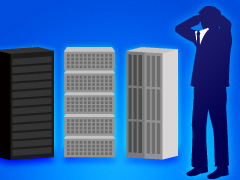
社内アプリケーションをとにかくパブリッククラウドに移行すれば良い、と考える企業も少なくない。だが本当にそうだろうか。移行前に3つの質問に答えられないとその移行は間違っているかもしれない。

オンプレミスのデータベースをクラウドへ移行する企業が出てきている。「Oracle Database」から「Amazon EC2」インスタンスにデータを移行する最適な方法は。

IaaS市場は統合が続いており、クラウドユーザーは新しい難題と危機に直面するだろう。しかし悪いニュースばかりではない。

ITアナリストは、全てのクラウドスタックの層で2016年に大幅な導入増加を予想している。その筆頭はIaaSで、ハイエンドのサービスの魅力がさらに増すと見ている。

近年、プライベートクラウドからパブリッククラウドへ移行する企業が出てきている。中でも日本通運はAWSとIIJのマルチ体制を取った点がユニークだ。移行プロセスも緻密に計画。注目プロジェクトを担当者が語った。

ハイブリッドクラウドの根幹である「プライベートクラウドとパブリッククラウドをどのように接続するか」をテーマに、SDNを用いたネットワーク構成、主要なパブリッククラウドの接続方式について解説する。

採用に積極的な企業も増えつつある「コンテナ」。その管理ソフトの代表格である「Docker」のコンテナが、「Amazon Web Services」で利用できる。ただし、利用に当たっては注意点もある。

AWSとSoftLayerのセキュリティ機能とロードバランサー機能を比較する。セキュリティ機能では、ファイアウォールやIDS/IPS、WAFを取り上げる。

パブリッククラウドのネットワークにフォーカスし、主要サービスの仕組みや特徴、料金を比較する。第1回ではAWSとSoftLayerを取り上げ、ネットワークの仕組みを比較した。

データおよびストレージの管理者は、ハイブリッドクラウドのシナリオに着手する前に、本稿で紹介する4つのステップを予備計画に加えることをお勧めする。

アプリケーションコンテナ技術「Docker」のクラウドサービスを進めるAWSとGoogle。2社が提供するサービスの違いについて紹介する。

クラウド利用で常に議論される「セキュリティ」に対する懸念。その責任所在の境界線は、サービスプロバイダーや利用サービスによって異なる。AWSの場合を見てみよう。

米Googleのクラウド機能を米VMwareの「vCloud Air」に組み込むことで合意されたのは、大きなニュースだ。だが、パブリッククラウドを使っていない企業にとってはあまり実用的なものではないとの見方がある。

価格競争から新しいツールやサービスに至るまで、2014年のクラウド市場は話題に事欠かなかった。2015年も同じような状況が続くのだろうか。クラウド専門家が予想する。

米Amazon Web Servicesの「Amazon Web Services」(AWS)は、2014年に約450の機能をリリースした。本稿では、その中からえりすぐりの機能を紹介する。

ヴイエムウェアの新しいクラウド「vCloud Air」を事前検証したユーザー3組が、同社への期待を込めて辛口批評を繰り広げた。ヴイエムウェアは仮想化基盤で作り上げた実績と信頼をクラウドでも構築できるか。

KVHは、アジアの主要な100カ所のデータセンター間を接続する「DCNet」サービスを、2014年8月から開始することを発表した。

Amazonは、「Amazon Web Services」(AWS)を「Amazon.com」と同じくらい簡単に使えるようにすることを目指しているが、多くの企業は依然として「どこから始めたらいいのか」という基本的な問題に頭を悩ませている。
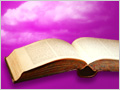
AWS(Amazon Web Services)が提供するデータベースサービスには、「Amazon RDS」「Amazon DynamoDB」「Amazon ElastiCache」「Amazon Redshift」の4つがある。それぞれの特徴とユースケースを紹介する。
パブリッククラウドには、データベースやファイアウォール、ロードバランサー、ミドルウェア、アプリケーションなどとして提供されるクラウドサービスが含まれる。ユーザー企業は複数のクラウドサービスを組み合わせて、業務システムを構築できる。大抵のパブリッククラウドは月額制や、利用した量だけ支払う従量課金制の料金モデルを採用している。
パブリッククラウドの主なメリットは以下の通りだ。
パブリッククラウドは、オンプレミスのデータセンターに代わるインフラの構築手段になる。パブリッククラウドでは基本的に、クラウドベンダーがITインフラを構築し、インターネットまたは専用線を通してユーザー企業に提供する。パブリッククラウドは、しばしば「ユーティリティーコンピューティング」と呼ばれることがある。ユーティリティーコンピューティングとは、水道、ガス、電気通信などの公共料金(ユーティリティー)と同様に、リソースやアプリケーションを利用したい量だけ料金を支払って利用できる形態を指す。
クラウドベンダーは、アプリケーションの構築と実行に必要なインフラを提供するだけでなく、セキュリティ対策ツールや監視ツールなど、ユーザー企業がアプリケーションを運用するためのツールも提供している。
主要なパブリッククラウドには「Amazon Web Services」(AWS)や「Microsoft Azure」「Google Cloud Platform」などがある。それよりも小規模なニッチクラウドもある。大手クラウドベンダーは、さまざまなクラウドサービスを提供しており、ユーザー企業はそれを幅広い用途の業務システム構築に利用できる。ニッチクラウドのベンダーは、特定の用途に特化したサービスを提供する傾向にある。
ユーザー企業がオンプレミスインフラからパブリッククラウドに移行する理由は幾つか挙げられる。例えば新しいアプリケーションを構築する際に、既存のデータセンターでは実現できないインフラの要件を満たすために、パブリッククラウドを採用することがある。コスト削減やデータ処理の高速化、インフラのメンテナンス作業の負荷軽減、冗長性の確保などのためにパブリッククラウドを利用する場合もある。
利用するクラウドサービスを決めたら、次はデータとアプリケーションをクラウドサービスに移行するための方法を決める必要がある。データをオフラインで移行する場合は、データを保存して持ち運び可能なハードウェアに自社のデータをコピーして、そのハードウェアをクラウドベンダーのデータセンターまで運ぶ。オンラインでデータを移行する場合は、インターネットまたはクラウドベンダーが提供するプライベートネットワークサービスを通して、データを転送する。
転送するデータ量が多くなるほど、時間とコストが掛かる。一般的にはオフライン移行の方が高速で低コストだ。オンライン移行は、移行するデータ量がそれほど多くない場合に適している。
アプリケーションをクラウドサービスに移行する方法も幾つかある。リフト&シフト方式は、アプリケーションのソースコードを再設計することなく、そのままクラウドサービスのインフラに移行する手法だ。リフト&シフトの注意点は、アプリケーションが移行後に正常に動作しない場合があることや、オンプレミスインフラを利用していたときよりもコストが増大する可能性があることだ。
こうした問題が起こることを防ぐために、移行前にアプリケーションのソースコードをクラウドサービスに適した形式に再構築するリファクタリングという手法を採用することができる。リファクタリングはリフト&シフトよりも多くの移行期間を必要とする傾向にある半面、クラウド移行後のアプリケーションの運用コストを抑えたり、処理速度を向上させたりする効果が見込める。他の移行方法として、古いアプリケーションを廃止し、クラウドサービスに適したアプリケーションを一から構築する方法もある。
クラウドベンダーは、クラウド移行を支援するためのツールを用意している。サードパーティー製の移行ツールを利用することも可能だ。
パブリッククラウドで利用できるリソースは、基本的には仮想化されている。データの送受信には、インターネットや専用線を利用する。パブリッククラウドでは、複数のユーザー企業がインフラを共有して、それぞれのアプリケーションを実行する。こうした設計の仕組みをマルチテナントと呼ぶ。データとアプリケーションはテナントごとに論理的に分離されるため、他のテナントのデータやリソースを利用したり閲覧したりすることはできない。
クラウドベンダーは、パブリッククラウドを運用するために複数のデータセンターを運営していることが一般的だ。同一の地域にあるデータセンター群を「リージョン」と呼び、リージョン内に存在するさらに小さいデータセンターの単位をアベイラビリティゾーン(AZ)と呼ぶ。リージョンやAZは一般的に、可用性を確保するために2つ以上の物理データセンターで構成されている。
ユーザー企業は、自社のセキュリティ要件やエンドユーザーへの物理的な近さに基づいてリージョンとアベイラビリティゾーンを選択する。アプリケーションを実行するためのインフラに複数のリージョンとアベイラビリティゾーンを利用することで、冗長性を確保し、システム停止のリスクを抑えることができる。