
安価かつ小型なコンピュータとして登場した「Raspberry Pi」は、さまざまな目的で使われている。想像以上に幅広い、Raspberry Piの“意外”な用途を紹介しよう。

スタンフォード大学の研究によると、在宅で「Apple Watch」を用いて6分間歩行距離試験を実施したデータは、臨床的に正確で有意義な洞察をもたらす。その事実は、医療機関や患者にとってどのような意味があるのか。

JavaScriptで独自アプリを開発・実装でき、TensorFlow Liteを利用したAIアプリも作れる。ハードウェアは分解も容易。そんな開発者を刺激する要素満載のスマートウォッチとは?

米国では「自律型ドローン」の実用化に向けて活発な議論が進み、食事の配達や工業設備の点検などさまざまな用途に期待が集まっている。ただし、いまだ技術的な限界も少なくない。

あらゆるものをネットワークに接続してそこから得たデータを活用しようというIoT。今や「そんなこといっても段ボール箱は使えないでしょう、はっはっは」と笑っている場合ではない。

電子メールの確認やフライト状況の確認、リマインダーなどApple Watchには多くの便利なビジネスアプリがある。どのような種類のアプリがあるのか紹介する。

多くの企業が、モバイルデバイスのコンプライアンス維持に必要な作業を理解していない。その背景には何があるのか。現状を整理する。

ウェアラブル端末やIoT(モノのインターネット)など、ネットワークにアクセスする新しいモバイル技術が次々と出現する中、企業はどのように対処すべきだろうか。EMMベンダーの幹部に市場のこれからを聞いた。

コンシューマーの間で利用が広がりつつある小型無人飛行機「ドローン」。そのビジネス活用を模索する動きが現れつつある。ドローン活用の現状と、その課題を整理する。

IoT(モノのインターネット)デバイスは、企業が実用的なデータを生成することに注力しなければ、単なる目新しい試みで終わる可能性がある。

企業のIT管理者はユーザーによる入力や対話操作の増加を見越して、視線認識や音声認識に注目している。だが没入型コンピューティングはまだ初期の段階にある。

米Googleのウェアラブル端末「Google Glass」は、プライバシー保護の面で世間から痛烈な批判を受けている。その強い風当たりを和らげるため、同社は新たな一手で勝負に出た。

ウェアラブルコンピューティングでは、USBスティックほどの小さなデバイスを使って、リアルタイムに処理されるデータを収集できる。だが、ウェアラブル端末の大半は単一用途だ。

次の本命技術と目される「ウェアラブル端末」。ユーザーの生活や仕事の仕方をどう変えるのか。その影響は未知数であるが、実際に活用が始まっている分野もある。企業は今、ビジネスでの活用方法を模索すべきだ。

「モノのインターネット」は一時的な流行ではなく、企業のビジネスを大きく変える可能性を持つ。IoTが普及した社会ではどのような生活を送ることができ、何が課題になるのだろうか。

ユーザーがスマートフォンやタブレットを会社に持ち込んでいるのなら、ウェアラブルでもそうしないはずがない。ウェアラブルデバイスはまだブレークしていないが、備えるのに早過ぎるということはない。

心拍数の計測機能を搭載した腕時計やスマートフォンが普及している。運動中や睡眠時など常に心拍数を計測する行為が習慣化したことで、今後の医療を大きく変える可能性が生まれ始めている。

次の本命技術ともいわれるウェアラブル端末。米Googleの開発するメガネ型端末「Google Glass」を、英国の航空会社Virgin Atlanticが試験導入する。よりパーソナルなサービスを提供し、顧客満足度を向上する狙いだ。
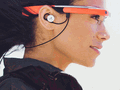
Google Glassなどのウェアラブル端末には、プライバシー侵害など懸念も少なくない。だがその機能や特徴を生かそうと、業務利用を見据えたアプリ開発は確実に活発化している。

注目を集めるウェアラブル端末はユーザーの生活や仕事の仕方をどう変えるのか。スマートウオッチやスマート眼鏡の活用で生まれる新しいワークスタイルや課題を解説する。