
IT関連のニュースや技術を追い続けている訳ではない経営層に、最新のIT関連情報の説明を求められたら――。今回は、Cloudflareの大規模障害を事例に、困った時にすぐ使える説明用スクリプトを紹介する。

クラウド全盛期を迎えても、企業はいまだにオンプレミスのレガシーシステムに依存している。「技術的負債」を抱えた状態で、無理なシステム移行をせずにAI活用を進めるにはどうすべきか。事例を基に解決策を探る。

企業では、IT部門だけでなく、事業部門の人材が自らITを活用する民主的なアプローチが広がっている。ただし、データ統合を民主的にしようとする場合には注意点がある。

アプリケーションを使うほど、企業はデータのサイロ化に悩むことになる。企業の規模が大きいほど問題は深刻だ。将来的にも持続可能なアプリケーション間の接続を管理する方法とは。

SaaSの採用を広げた結果として、データのサイロ化に悩んでいる企業は珍しくない。分散したデータを統合するには、どのような戦略が必要なのか。

企業が複数のSaaSを利用するとき、データの保管場所や管理手法がばらばらになればデータ活用は簡単ではなくなる。こうした課題を解消するために、市場にはどのような製品が登場しているのか。

企業が業務のために複数のSaaSを利用することは当たり前になった。こうした状況で問題となるのは、SaaSやオンプレミスシステム間のデータ連携だ。データの相互運用性を保つ方法とは。

企業はCOVID-19の感染が拡大する中でも事業を継続するために、SaaSの導入を急速に進めた。その結果、社内に存在する複数のSaaSが、“ある問題”を起こすようになった。その問題とは何か。

企業内の各部門がSaaSを勝手に導入することが、企業のITシステムのサイロ化を引き起こしている。SaaSベンダーが開発する連携機能は、サイロ化の解消にどう役立つのか。連携の具体的な方法とは。

気軽に導入できることから企業はさまざまなSaaSを利用するようになった。各部門が自由にSaaSを導入した結果、サイロ化が生じている。企業が目指すべきITシステムの全体像を踏まえ、現状を分析する。

企業活動の中核からニッチな分野まで、幅広い業務向けのSaaSがある。その手軽さから、事業部門がIT部門を経由せずにSaaSを導入することは珍しくない。その活動から、企業にとっての予期しない課題が生じている。

サブスクリプション形式で利用するSaaSの管理をおろそかにすると、必要のないサービスや機能にコストをかけてしまうことがある。身近な“あるアプリケーション”が契約管理に有効だ。

クラウドサービス形式のRPAソフトウェア「クラウドRPA」は、管理者のbot管理を容易にする。具体的にどのような管理面のメリットをもたらすのか。

SaaSは多くの企業にとって不可欠だ。だが柔軟性に欠け、統合と管理にまつわる問題を抱えている。既存のオンプレミスシステムを維持しながら、拡大するアプリケーション環境にどのように対処すべきか。

ソーシャルコラボレーションツールは、共同作業を促進し、生産性を高める。だがなかなか使い始めようとしないユーザーも少なくない。実際導入した企業はどのように、導入を進めたのか紹介する。
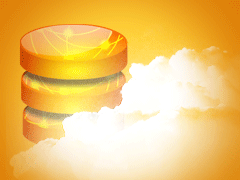
クラウドバックアップにはメリットがあるものの、その技術が企業などの“組織”にとっていつも都合がいいものとは限らない。オンプレミスのバックアップが信頼できるケースはまだまだある。

ニューヨーク証券取引所で先頃発生したシステム障害は、ゲートウェイのソフトウェアを更新した際の設定の不備が原因と発表された。これは自動化によって防げることだ。

米Googleで発生した2011年のメール障害。そこから得られた教訓は、実に興味深いものだった。Googleスタッフが明かした障害復旧の舞台裏を示す。

SaaSの普及で「勝手クラウド」がもたらすリスクが組織全体に広がっている。勝手クラウドが革新を生み出すことがあったとしても、クラウドに伴うセキュリティリスクのためにその価値は相殺される。そろそろ管理すべき時だ。